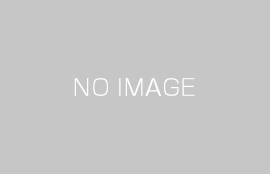昔からずっと画家たちは、どんな風に「光」を絵画に表現してきたのでしょう?
この、「光」をどんな風に「絵」に描いたらいいのか?
が分かると
どんなジャンルの絵を描くときでも「光」を描くことができます。
今回は「光」を描くための「色彩」についてご紹介します。
光を描くという事はどうゆうこと?

光を絵に表すためにはまず
色彩を科学的に理解すると、とても分かりやすく、絵を描く時に考え込まなくて済むようになります。
科学的に、というとなんだか難しそうに感じるかもしれませんが、基本は「赤・黄・青」の三色だけで、あとはその応用なので難しく考える必要はないのです。
大昔から画家たちは
「光」を絵画として表現することに試行錯誤してきました。
その試行錯誤を時代にそって紹介していきたいと思いますが
時代の流れとともに「光」をどのようにとらえて「絵」に表現してきたのかが分かると、どんな風に描いたらいいかのヒントが得られると思います。
光を描く方法について画家たちは試行錯誤してきた

「光」をどう描くかについて画家たちが表現してきた方法は、時代の移り変わりで変化してきています。
化学的な物事が全く解明されていない中世ヨーロッパでは
絵画はキリスト教の教えを広めることが目的だったので「神様(キリスト)=光」という考えで絵を描いていました。
なので、この時代は光はキリストの後光の光を金箔を貼るという事によって表現していたという感じでした。
この時代の絵画には、金箔がたくさん使われています。
金箔=光というわけなのですね。
↑ 上の画像は中世の画家「ジョット」が描いた「受胎告知」という絵画です。
右に描かれているのが聖母マリアなのですが、頭の周りに金箔で後光が描かれていますね。
そして、左側に描かれている天使ガブリエルにも頭の周りに後光が描かれています。
こんな風に、光=神様の考え方のもとに、光は表現されてきました。
ルネッサンス時代(15世紀)になると
キリスト教をテーマに絵は描かれていましたが、このころになると、描かれるキリストやマリア像が生身の人間として描かれるようになってきます。
レオナルド・ダ・ヴィンチが、空気遠近法や透視図法を利用して現実的な空間の中にリアルな人間としてのキリストやマリアを表現しました。
このころはまだ、「光」そのものを描こう、という概念が画家たちの中では生まれていなくて
まだまだ、キリスト教とギリシャ神話を題材に絵は描かれていました。
「アトリビュート」
と言って、絵の中の人物が「何の持ち物」を持っているか、とか
身に着けている洋服の色から誰であるかといったことを、当時の人達は判断して絵に何が描かれているのかを理解していたのですね。
「アトリビュート」については
の記事で説明してあります。
バロックの時代(17世紀頃)になると
光を表現するために、光が当たっていない部分を暗くすることで、光を際立たせる手法で描いていました。

「夜警」
1642年
上の画像は17世紀のオランダの画家レンブラントの作品「夜警」というタイトルの絵なのですが
実は、夜の情景を描いた絵ではなく、昼間の集団肖像画なのだそうです。
当時のアムステルダム市長「フランス・バニング・コックの依頼で描いたものなのですが、正確なタイトルは決まっていなくて
「バニング・コック隊長率いる火縄銃組合の人々」と呼ばれることもあるそうです。
「夜警」というタイトルは、のちの人々が、絵の画面の暗さから名付けたそうです。
17世紀のバロック絵画の特徴は、このように、光を表すためにあえて周りを暗く表現することで、描き出していました。

17世紀の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールもまた、光を表現するために、画面を暗く表現しています。
それから、時代が流れて19世紀になると、
科学技術の発達によって、今までになかった絵具の顔料(色)が科学的に作られるようになりました。
使用できる色が増えたのですね。
それから、1840年頃には写真が発明されました。
こういった、化学技術が急速に発達したことと、写真の登場によって、絵画に大きな転換が起きることになりました。
光を描く方法は絵具の色の数が増えた事と写真の登場によって180度考えが変わった

科学技術の発達は「絵画」の世界に大きな変革をもたらしました。
一番最初に今までの絵画の描き方を覆す、新しい描き方をしたのは「マネ」という画家でした。
↑ 上の画像は マネの作品「笛を吹く少年」という作品です。
この絵は、実在する人物を平面的な背景の中に描いています。
今、見ると、ごく当たり前の絵画表現のように見えるのですが、当時としては実在する不特定の人物を描くことはありえないことでした。
それに、背景も平面的に一色で塗りつぶすという描き方はしなかったのです。
マネは、当時発明された写真と、日本の絵画に影響を受けてこの絵を描いたようです。
当時、こんな描き方は絶対にありえなかったようで、サロン(フランスの画壇のようなところ)では
驚きと批判を受けていたようでした。
それから、もう一つ、絵画の概念が180度考えが変わるような出来事があったのですが、それは
ドイツの文豪「ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ」(1749~1832)が
「色彩論」
を発表したことでした。
この、「色彩論」は、現代アートの起源になった考え方なのですが
「黄色と青の粉末をすり混ぜると肉眼には緑色にみえるけれど、拡大鏡で見ると、黄色と青色を区別して見ることが出来る」
ということが書いてあります。
これはどうゆうことかというと
2つの異なる小さな色の点は、近くで並べられた時にはそれぞれの色が並べられているように見えるのですが、離れて見ると視覚的に混交された別の色となって見える、ということなんです。
これをうけて、画家「スーラ」は
点を並べて描く手法で絵画を制作しました。
↓ 下の画像はスーラが点を並置させることによって描いた作品です。

「グランド・ジャット島の日曜日の午後」
1884~1886
この手法は現代の印刷やテレビ画面の画像に利用されている事とまったく同じことなんです。
こういったような、「ゲーテ」の「色彩論」に始まる色と色の光学的な関係が次々と明らかになっていくことで
当時の画家たちは、光学的に認識される色彩を、絵画の色使いとして表現することに関心を向けるようになっていったのですね。
光を表現しようとしてきた印象派の画家たち

「日の出」
1873年
「印象派」と言われる画家の中でも
画家クロード・モネは「補色」を使って絵画を制作しています。
モネは、「色彩論」で「補色」という概念がでてきたことによって、絵画を構成する単位として、補色関係の色どうしを認識し始めて絵に表現するようになりました。
「補色」とは、色相環で向かい合った反対の色どうしのことを言います。
色相環については
の記事で紹介しています。
当時の「サロン」(フランスの画壇)では、モネがこの光学的な色彩の理論から絵画の制作を試みていることが理解されなくて
「モップで絵を描いたみたいだ」とか
「まるで下書きの絵だ」といったことを言われて
認めてもらえませんでした。
そこで、モネと同じ考えを持つ画家たちがあつまり、サロンとは別に展覧会を開いたのが、印象派の始まりということなのです。
印象派という名前は、モネなどの画家たちを批判して、評論家たちが付けたネーミングらしいです。
こうして、印象派と言われる画家たちの登場によって、今までの古い考えや価値観が変わって、現代アートにつながるような活動がうまれたのですね。
光を描くために現代の画家たちは光学理論を利用している

今では当たり前に思っている三原色である「赤・青・黄」も
中世からルネッサンス、そしてバロックから印象派と時代が流れていくつれて少しずつ色彩のことが解明されて、絵に表現されてきたことが分かったのではないでしょうか。
具象的な絵画を描く上で、色彩の理論を知ることはとても重要で
そのことを理解してはじめて、色彩をどのように使ったらいいのかが分かります。
理屈を知ることによって、描きたい絵を描けるようになるという事です。
現代でも、印象派の「モネ」のよう、補色を利用して描いたり、
スーラの絵画のように、原色に近い色を点で置いて絵を表現しています。
光を描く方法について詳しく知りたい人におすすめの本

ずっと絵を描いてきて感じることは、
目で見えた色をそのまま画面に乗せただけでは、現実に存在しているような絵は描けない、ということです。
写実的な絵を描いていると、
目に映った色を絵具で表現するという事と、「絵にする」ということがまた違うことであるということに気づかされます。
絵の具は、色なので隣に置かれている「色」の影響で見え方が違って見えるからなのですね。
上記に書いたように、
隣り合う色どうしは離れて見ることによって、二色が混色されたような色として人間の目は認識します。
印象派の絵画のように
対照的な色を点で隣り合わせに配置することによって、その色がいきいきと交じり合って見えることを利用して描くことが大切なんですね。
具体的に光を絵に描くための内容が書かれている
私のおすすめする本は
ボーンデジタル出版 カラー&ライト リアリズムのための色彩と光の描き方
です。
具体的な色彩の理論と光をどのように描いたらいいかが、豊富な絵画画像と共に掲載されています。
色彩の理論は学校などで学ぶけれど、
それをどう使って絵画表現に行かしたらいいのかが分からなかったのですが、
この本は、その具体的な方法がすべて網羅されていました。
もっと早くこの本に出合うことが出来たらよかったのに、と思います。
私自身がずっと絵を描いてきて感じることは、「色彩」はとても重要な絵画の要素だということです。
魅力的な絵を描く上で色彩は欠かせないものなので
色彩の理論的な事と、絵具の顔料といった材料の特性の2つのことを
勉強しないといけませんね。
モチーフの描き方の本や、具体的な○○の描き方といったノウハウだけでは
自分だけのオリジナルの絵を描きたいと思った時に行き詰ってしまいます。
もし、あなたが、
絵を描いていて、行き詰ってしまったら
これらの知識をもう一度勉強してみるのも一考かもしれませんよ。
光を描くときの光の色について


光を描くときの色を、見えたままの色で描こうとすると、「白」を使ってしまいがちではないですか?
私は最初の頃は、光を「白」の絵具で塗っていたのです。
目に見えたままの色を乗せて描いていたからなのですが
これはみんなが意外とやってしまいがちな事だと思うのです。
実は
光学的なことでいうと、光は「黄色」なのですね・・・。
そのことを、ゴッホは理解していたのだと思います。
上記の絵画画像のように、光を「黄色」で夜の闇の色を「黄色」のほぼ反対色の濃紺で描いています。
月夜の暗闇で色彩を見分けて描くのは困難です、きっとゴッホは、記憶とイマジネーションを頼りにこの絵を描いたのでしょう。
まとめ
「光」を絵の中に描くためには「色彩」について学ぶことが一番の近道ということが分かったのは比較的最近のことなんです。
美術の学校で理論的なことは学んだことは学んできたけれど・・・・
それを、どのように絵画の制作に役立てたらいいのかずっと分からないままでした。
絵画教室で学んでいたときに、先生が「デッサンばかりやっていても魅力的な絵は描けないんだよ」そんなことを言ったのを聞いて
今までの考えは思い込みだったと分かったんです。
それまでは
美術大学受験のために先生は言っていたからかもしれませんが、デッサンが一番何よりも重要と聞かされてきていたせいもあり
デッサンができると素晴らしい絵が描けると思い込んでいたようなのです。
もちろん、デッサンもとても絵を描く上では需要な要素なのですが、
それだけじゃなかったのです。
ずっとデッサンをストイックに勉強してきたこともあるし、色彩については「生まれつきのものだから」ということを周りの人達が言うのを聞いたりしていたので
そうゆうものなのかな・・・と思っていたんですね。
だけど、だんだんと絵を学んでくるうちに、
もしかしたら、「色彩」は生まれ持った感性ではなくて、勉強で誰でも色彩的に魅力的な絵が描けるのだと思ったのです。
この記事で紹介した本
カラー&ライト リアリズムのための色彩と光の描き方
では、そのことが具体的に記載されていて、本当にもっと早くにこの本にであって
いればな・・・、という気持ちになるくらいおすすめの本でした。
「色彩」に関する書籍もたくさん出版されていますし、
現代では調べるとたくさんの情報が手に入ります。
「この記事をきっかけに、「色彩」と「光」をもう一度学びなおして、いろいろな「光」を絵画の中で描けるようにしていけたらいいですね。
私もまだまだ、学びの途中です。
「色彩」についての理解を深めて、「光」を描けるようにしていきたいなと思っています。
いつも、読んで頂きありがとうございます。