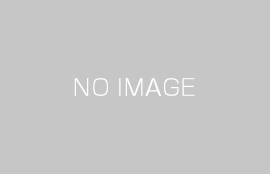配色の組み合わせに悩まない方法?
こんにちは。
絵を描くときの色って、どうしてますか?
なんとなくの感覚で色を塗っていませんか?
じつは、私はずっと、色について、なんとなくの感覚で色を選んで塗っていたんです。
だけど・・・。
何年も絵を描いていくうちに、自分なりの「色」の決まりが出来上がってきたのです。
本格的に一定の基準で色を決めるようになったのは、
仕事を退職して、絵画教室に通いだしてからなんですよ。
それまでは、
「影」「陰」の色に「茶色」を使っていたんです。
「かげ」には2つの「かげ」があるんですね。
物体の光の当たっていない部分にできる「陰」と、物体と地面に接している所に出来る「影」の二つのことです。

色の特性や、色の見え方について論理的に勉強して分かったから
茶色を塗ることはしなくなりましたが、
絵って、見えたままの色を画面の上に再現するだけじゃ、だめなんだ!
・・・ということが分かり、
「理屈」で知ることも大切なんだ!!
と、目から「ウロコ」の出来事でした。
見えたままの色を作って塗るんじゃなくて、「色」をある「決まり」によって塗るだけで素敵な「絵」を描くことができます。
これは、絵だけじゃなくて「デザイン」「イラスト」「漫画」の絵を描くときにも役に立つと思うので、
覚えて
使ってほしいなと思います。
配色は生まれつきのセンスじゃなかったんです

どんな色を使って塗ったらいいか分からなくて困っている。
絵を鉛筆で描くところまではうまくいくんだけど、色塗りで失敗しちゃうんだよね。
で、あれば
「色」について少し勉強してみましょう。
これも、才能ではなんいんです。
色の決まりを理解するだけで、配色も混色も、感覚に頼らないで自信をもって塗ったり配置したりできるようになりますよ。
私がきちんと色について勉強したのは、働きだしてからで、デザインや広告・印刷に関する授業をしなくてはならなかったため勉強したからなんです。
その当時は「商業高校」で
商業の科目の中にデザインや広告・印刷の授業が組み込まれていたんですね。
それから、「販売士検定試験」というものがあって、
販売員の資格検定の中には、色彩に関する知識が問題として出題されていたために
色彩の授業も教えなくてはならなかったからなんです。
ディスプレイの勉強なんかもしました。
それから、
別の学校では「色彩検定」を1年間ずっとそればかりで教える授業があって、
「色彩検定」についても自分で一生懸命勉強したことがあります。
色の三原色から学ぶ色の作り方
「色」の三原色はもちろん誰も知っていると思うのですが・・・・。
「赤」と「青」と「黄色」ですよね。

その、「赤」にも2つの種類の赤があるのは知っていますか?
同じように、青も黄色も2種類あるんです。
赤も、黄色み寄りの赤と、青み寄りの赤です。
青も赤味寄りの青と、黄色み寄りの青。
黄色も赤味寄りの黄色と、青み寄りの黄色というように。
そして、絵具のセットの中には、必ず2種類の赤・青・黄は入っています。
「きれいなオレンジがつくれないんだよ」
そういう生徒は、色相環で離れた場所にある、黄色と赤を混色して作っているんですね。
三原色を混ぜると、「二次色」といって、
赤と黄色を混ぜて「オレンジ色」が出来ます。
黄色と青を混ぜて「緑色」が出来ます。
青と赤を混ぜて「むらさき色」ができます。
それらを「二次色」といっていますが、この時に
色相環で離れた色どうしを混ぜるとくすんだ、色味の二次色が出来上がってしまいます。
それはそれで、影に使用したり、写実的な絵を描く時に遠くにあるものを描く時に使えるので、
ダメな色ではないのですが、
綺麗な色が作れなかった・・・となってしまうんです。
例えば、オレンジを作りたかったら、
色相環で、赤に近い黄色と黄色に近い赤を混ぜると発色の良いオレンジ色が作れます。
油絵の具で具体的に名前でいうなら、
パーマネントイエロー(カドミウムイエロー)と、カドミウムレッドを混色すると綺麗なオレンジが作れます。
(綺麗な、というのは彩度の高い純色に近い色味の事です)
これを、レモンイエローと、カーマインを混色すると、彩度(鮮やかさ)の低い、落ち着いた色のオレンジができあがります。
実際に混色をして、確認してみてください。
これ、意外とみんな知らなくて、やってしまいがちなので、
これだけでも知っておくと色を混ぜるときに綺麗な(彩度の高い)色が作れます。
それと、絵を描くときに、色味の幅が広がります。
色相環とは
こんな感じの色のサークルのことです。

「色彩検定」のテキストや美術の教科書に掲載されている「色相環」はマンセル表色系をつかったもので、
日本産業規格(JIS)の規格できめられた色の表示方法になっています。
検定受検しなくても、勉強だけでもやくだちます、テキストは一般の書店で取り寄せることができます。
大きな書店では置いてあることもあります。
暖色と寒色はどの色にもある

小学生のころ、赤は暖色で、青は寒色で・・・と教えてもらったことがあるんじゃないかと思いますが、
どんな色にも、寒色と暖色があるっていったら驚きますか?
私の色に対する考え方なので、これを知っていると、どんなジャンルの絵を描く時にも役に立つと思うので、
この考え方を使ってみて下さいね。
赤でも、温かい赤と冷たい赤があります。
さきほど紹介した、黄色に近い赤が温かい赤で、青に近い赤が冷たい赤です。
同じように
黄色も、青も、赤に近い方が、温かい色で、青に近い方が冷たい色になります。
これを知って
「絵」を描いて色を塗る時に、画面の中に寒暖のバランスが良くなるように色を塗っていくと素敵な絵になります。
色相環を知れば配色と混色に迷わない
色相環の画像が頭の中に入っていれば
色相環をもとに、配色と混色を決めることができるので、考え込む時間がなくなり
どんな絵でも、どんな光が差し込んでいても描くことが可能になります。
そして
こんなイメージで描きたいと自分のイメージを絵で表現できるようにもなります。
類似色

類似色は色相環で近い色どうしのことをいいます。
類似色を使うことで、まとまりのある、落ち着いた画面をつくることができます。
色相環で近い色どうしの組み合わせを作ると、落ち着いたまとまりのある配色にすることができます。
補色

補色は色相環で向かい合わせになっている色のことをいいます。
黄色の向かい合わせになっている色は紫なので、黄色と紫は補色同士の色の関係ということになります。
この、補色どうしの色の組み合わせはコントラストが強くなって、インパクトのある配色になります。
巨匠の絵から配色をまねてみる
難しいことは抜きに
手っ取り早く、素敵な配色を作りたいという方は、
「巨匠」といわれる画家の絵を鑑賞して、配色を真似してみてはいかがでしょうか?
私も参考にして絵を描いています。
特に参考にしているのは
「印象派」のモネの配色です。

モネの作品は影・陰のつけ方や色使いを参考にしています。
陰に黒や茶色は使っていないんですよ。
「モネ」の作品を観る時は、陰・影の色についてよく見てほしいです。
それから、ゴッホの作品も


ゴッホの作品は夜をどんな色で描いているかを参考にしています。
「ゴッホ」の作品も、黒や茶色で陰影をつけていないので、参考にしています。
まとめ
独学で勉強しよう!
そんな風に思っても、美術用語を知らなければ
どのように学んだらいいか分かりませんよね。
ゴッホもフランスの美術学校で学びました。
色彩のことをかなり勉強したようです。
この、色相環というものがあるのだ、それを利用すると
色彩をどのように使用して絵を描いたらいいのかが
分かるらしい。
そんなことだけでも、分かっていただけたら嬉しいです。
色彩や配色のことは、公の教育機関では学ぶことができません。
ひだまり絵画教室では、この色彩の知識を活かし方を学ぶことができる
絵画教室です。
色相環を覚えて、ぜひ、絵の制作に活かしてみてはいかがでしょうか。